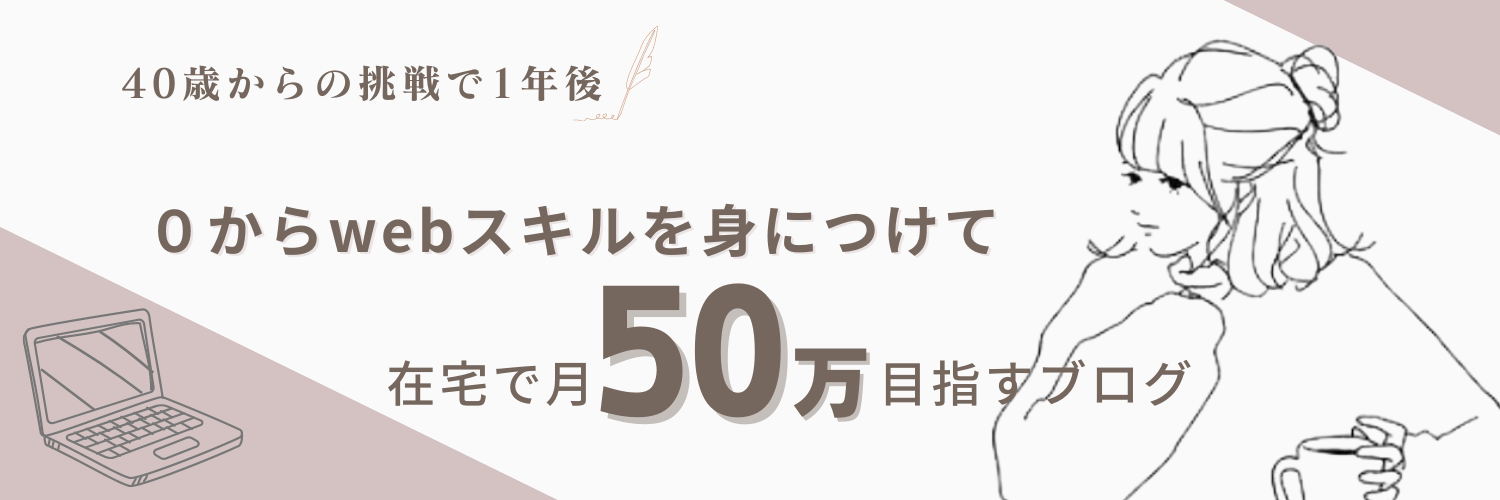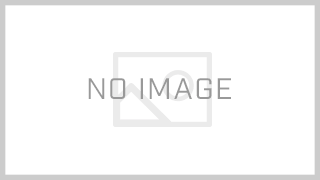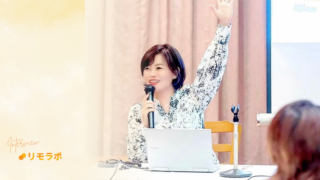最近、イラストや文章をあっという間に作ってくれる「生成AI」、本当にすごいですよね。短い言葉を入れるだけで、プロが作ったような作品が出てくるので、創作活動や仕事に活用し始めている人も多いのではないでしょうか。
とても便利な一方で、「これって著作権は大丈夫なの?」「知らないうちに誰かの作品をパクってない?」といった不安の声もよく耳にします。
そこでこのコラムでは、生成AIと著作権の気になる関係について、「結局、何がOKで何がNGなのか」を、難しい言葉をなるべく使わずに解説します。安心してAIを使いこなすためのヒントが満載です!
第1章:AIに作らせたものは「自分の作品」になる?
まず一番の疑問、AIが作ったものは「自分の作品」として、著作権で守られるのでしょうか? この答えは、「あなたがどれだけアイデアや手間をかけたか」で決まります。
そもそも「著作権」って?
著作権法では、「著作物」をすごく簡単に言うと、「作者の【考えや気持ち】が【その人らしい形】で表現されたもの」としています。ただのデータや、誰がやっても同じになるものではなく、作者の【個性】が光っていることが大切です。
AI生成物でOK/NGなのは、こんなケース
この「作者の個性」をAIに当てはめてみましょう。
- 【NG】これだけだと、あなたの作品とは言いにくいケース AIに「猫の絵を描いて」と、一言だけ指示したとします。これだと、AIが自動で描いただけに近く、あなたの「考え」や「個性」が十分に入っているとは言えません。誰が指示しても似たような結果になるため、これだけでは著作権は発生しにくいでしょう。
- 【OK】あなたの作品と認められる可能性が高いケース 一方、あなたが明確なイメージを持って、AIを「道具」として使いこなした場合は話が別です。
例えば、 「【テーマ】雨上がりの路地裏。【主役】段ボール箱の中で寂しそうにしている子猫。【構図】上から見下ろす感じで、子猫の大きな瞳を強調してほしい。【雰囲気】全体的に青みがかった色で、街灯の光だけが暖かく差し込んでいる感じ。水彩画のような、にじんだタッチで。」
ここまで具体的に指示すれば、あなたの【アイデア】がしっかり反映されていますよね。さらに、AIが作ったものの中からイメージに近いものを選び、自分で色を調整したり、背景を付け加えたりする【手直し】をすれば、それはもう立派なあなたの「創作活動」です。
このように、人間が主導権を握ってAIを使いこなしていれば、完成した作品はあなたの【著作物】として認められる可能性が高くなります。
ポイント:AIに丸投げはNG!自分の作品にしたいなら、具体的な指示と自分で手を加える「ひと手間」が重要です。
第2章:どんなときに「著作権侵害」になる?
次に、一番気をつけたい「著作権侵害」の話です。これは、AIが「学ぶとき」と「作品を作るとき」の2つの場面で考える必要があります。
1. AIの「学習」は問題ないの?
AIは、ネット上にある膨大な画像や文章を「学習」して賢くなります。この学習データに、誰かの著作物が含まれていることは珍しくありません。
現在の日本の法律では、この学習行為は「作品を鑑賞するためではなく、パターンを分析するため」なので、原則としてOKとされています。
ただし、「特定の作家の絵だけを集中的に学習させて、そっくりな絵を描くAIを作る」といった、作家さんの仕事を奪いかねないようなやり方は、今後問題になるかもしれない【グレーゾーン】だと言われています。
2. AIが作ったものが「誰かの真似」になっていたら?
私たちがAIを使う上で、より直接的に注意すべきなのがこちらです。AIが作ったものが、既存の作品とそっくりだった場合、【著作権侵害】を疑われる可能性があります。
判断のポイントは、シンプルに以下の2つです。
- 元ネタを知ってて真似したか?
- 見た目(表現)がそっくりか?
ここでAIならではの落とし穴があります。あなたは元ネタの作品を全く知らなくても、AIが学習データとして知っていれば、「AIを介して真似した」と見なされる可能性があるのです。「偶然です!」という言い訳が、人間同士の場合より通りにくいかもしれない、と覚えておきましょう。
例えば、「有名なアニメキャラクターをそのまま描いて」とAIに指示して作った画像をSNSにアップしたり、「有名な写真家の代表作とそっくりな構図」の画像をコンテストに出したりするのは、著作権侵害になる可能性が非常に高い【NG行為】です。
ポイント:自分の知らないうちに、有名な作品とそっくりなものが出来上がってしまう危険性も。AIが作ったものは、必ずチェックが必要です。
第3章:トラブルを避けるための【5つの実践ルール】
では、どうすれば安心してAIを使えるのでしょうか?文化庁も「やっぱり人間のアイデアや工夫が大事」という考え方を示しています。それを踏まえて、私たちが今日からできる5つのルールをご紹介します。
- 【公開前にGoogle画像検索でチェック!】 AIが作ったものをブログやSNSに載せる前、商品に使う前に、似たような作品がすでにないか画像検索などで確認するクセをつけましょう。
- 【使うAIの「利用ルール」は必ず読む!】 AIサービスごとに、「作った作品の権利は誰のもの?」「商用利用はOK?」「もし問題が起きたら誰の責任?」といったルール(利用規約)が違います。特に「トラブルの責任は利用者が負います」となっていることが多いので、必ず目を通しておきましょう。
- 【どんな指示で作ったか「メモ」を残す!】 万が一「これは私の作品です!」と主張する必要が出たときのために、「どんなアイデアで、どんな指示(プロンプト)を出し、何回くらい手直ししたか」を記録しておくと、あなたが創作に関わった強力な証拠になります。
- 【会社で使うなら、社内の「共通ルール」を作る!】 職場でAIを使うなら、「このAIツールを使おう」「会社の秘密情報は入力しない」「公開前は法務部に確認する」といった共通ルールを作り、全員で守ることがトラブル防止につながります。
- 【お金が絡むなら「専門家」に相談!】 作ったもので商品を開発したり、大きな広告に使ったりするなど、ビジネスで重要性が高い場面では、自己判断は危険です。弁護士など著作権に詳しい専門家に相談し、安全な使い方を確認しましょう。
まとめ:AIは「優秀なアシスタント」、主役はあなたです
生成AIは、私たちの創作活動を助けてくれる、本当に便利なツールです。 しかし、それは「全自動の魔法」ではありません。あくまで、あなたのアイデアを形にするのを手伝ってくれる「超優秀なアシスタント」だと考えましょう。
そして何より大切なのは、AIが作ったものに対する最終的な責任は、AIではなく【道具として使ったあなた自身が負う】という意識です。
この心構えさえ持っていれば、著作権トラブルを恐れすぎることなく、AIとの良い関係を築いていけるはずです。技術や法律はこれからも変わっていくので、時々ニュースをチェックするくらいの気持ちで、新しい情報を追いかけていきましょう。